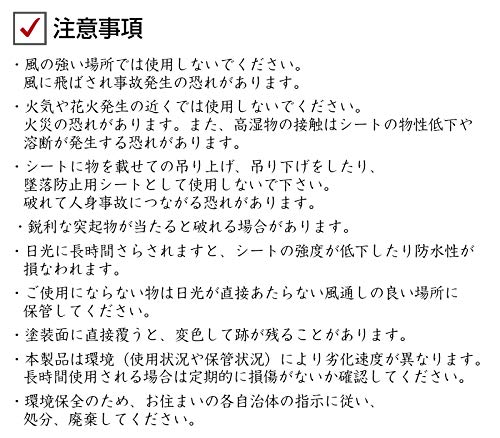住友化学園芸 レンテミン液剤
OTS UVシルバーシート
シンセイ 防虫ネット 1mm目 180cm×5m
植物を脅かすモザイク病
人間や動物を危険さらす病原菌はこの世界にはごまんと存在して、日々人々を悩ませていますが、植物も例外ではありません。野菜や果物、草木や花にはモザイク病という、ウイルス性の不治の病にかかってしまうリスクが常にのしかかっているのです。このウイルスは人にうつることはありませんが、植物にとっては生死を問う大問題です。今回はモザイク病とは一体なんなのか、原因、症状、対策など気になるポイントを解説します。
モザイク病にかかってしまう原因について
モザイク病の対策を講ずるには、まずは病気を発症させてしまう原因を掴むことです。モザイク病はウイルス性の病で、感染経路は主に液体が関係してします。アブラムシやダニ、シラミなどの昆虫が既に発病している植物の導管液や篩管液といった、草木の体液を吸って今度はほかの健全な植物の体液を吸うことで伝染病のように広まることが原因とされています。暖かい季節になると虫が媒介役となって、どんどん病を広めてしまうことが主な原因です。
人の手でモザイク病を広めてしまうことも
ほとんどの原因は虫の媒介にありますが、人の手で新たな感染経路を作ってしまうこともあります。モザイク病に感染した植物を手で触ったり、剪定バサミで枝をカットしたときに、モザイク病の植物の体液が手やハサミに付着してしまい次に触れた植物に病気を移してしまうことがあります。またモザイク病にかかっている作物を挿し木や株分けで増やしても、新しく生まれてくる作物はモザイク病をもって誕生することになります。
モザイク病は種にも伝染する
発病すれば治すことができない厄介な病気ですが、さらに追い打ちをかけるように厳しい現実があります。モザイク病の草木は、挿し木や株わけはもちろん、種から新しく栽培してもモザイク病を根絶することは難しいのです。モザイク病の原因は虫の媒介から始まり、人のケアレスミスや自然の働きによって引き起こされています。
モザイク病の土壌感染について
ウイルスに侵された液体が付着するだけでも感染する恐ろしいモザイク病。そんな強力なウイルスだから、土に対する影響も心配になってきます。しかしモザイク病は土壌感染は基本的にないと言われているのでご安心ください。植物の切り口からウイルスが侵入することはあるので、絶対とは言い切れませんが、土壌を介して根っこから病気が移るようなことはないので、1つの幹が感染しても、慌てて畑やプランターの土を捨てる必要はありません。
モザイク病は土壌感染すると勘違いしやすい
1つのプラントがモザイク病にやられてしまうと、凄い勢いで他の農作物も一気に全滅してしまうケースがあります。一見すると土壌感染によって畑全域がモザイク病のウイルスに侵されてしまったのだと勘違いしやすいですが、アブラムシの繁殖スピードからすれば、土壌汚染ではないことが分かります。アブラムシのメスは交尾無しで卵を産むことができるので、瞬く間に子孫を繁栄するため群れが畑に押し寄せれば、多くのプラントが食べられておかしくないのです。
モザイク病の症状について
モザイク病の症状は進行の段階ことにあらわれ方が異なり、軽度な症状ではほとんど気づかないこともあります。植物の葉っぱ斑点模様やリング状の模様が浮き出て、葉っぱの色が黄色や薄緑色に変色するなどの症状が一般的です。媒介されるモザイク病のウイルスによってたちまちですが、共通する症状は初期症状は葉っぱの異変から始まり、次第に茎、幹、といった順番で衰弱していくといった症状です。
葉っぱの先から植物へ症状が広がる
きっかけは葉先のちょっとした異変でしかありませんが、月日の経過と共に葉っぱは潤いを無くしシナシナによれてしまったり、茎や幹が細くなったりと植物全域に症状が広がります。果実がなる作物では、しっかり果物にも葉っぱと同様の症状がみられます。
モザイク病と呼ばれる由来
モザイク病にかかった植物は、若葉の先っぽから変色、変形、歪み、など変化をくり返し、次第に葉っぱの表面がモザイク加工をしたような斑な姿形になることからモザイク病と呼ばれています。チューリップなど一部のフラワーに発症する無害のモザイク病は、そのミステリアスなデザインから希少性が認められ価値のある花として海外で人気になった歴史がありますが、日本ではモザイク病と言えば悪いイメージしかないのが普通ですね。
モザイク病対策1:虫除け
モザイク病は現在の技術では治すことができない病気ですが、発症リスクを下げる対策を行っていけば、農作物や観賞用植物を守っていくことは可能です。まずは根源である害虫(アブラムシ)を植物に近寄せないことが先決です。
アブラムシが嫌う光の反射を利用する
農業ではマルチ栽培と呼ばれるシートを作物の周囲に張り巡らせることで、土の保湿や温度を高めて作物を大きく成長させる手法があります。この技術の主な目的は作物を育てやすくすることですが、その他の効果ではアブラムシを寄せ付けないメリットもあるのです。シルバーのシートを使用することで日光が反射されて、その光をアブラムシが嫌うことで、畑に害虫を寄せ付けないという相乗効果が生まれる仕組みです。
OTS UVシルバーシート
虫除けネットを張る
育てる作物によっては、防虫ネットを張って害虫対策をすることが可能です。防虫ネットは虫の侵入を完全に遮断する素晴らしい効果がありますが、反対に光の吸収を妨害したり蜂やテントウムシなど益虫との交流も絶ってしまうので、作る作物の特徴をよく理解して使用しなければなりません。
シンセイ 防虫ネット 1mm目 180cm×5m
モザイク病対策2:益虫を放つ
アブラムシは、寿命が1ヶ月前後とかなり短い生き物ですが、さらにその寿命を縮めるのが天敵テントウムシの存在です。テントウムシはアブラムシを捕食してくれるので、畑にテントウムシがいればアブラムシを綺麗に片付けてくれるのです。なのでテントウムシを農薬で撲滅させないことが重要です。畑に数十匹から100匹程度のテントウムシを放つことで、アブラムシによる被害を解消してくれるかもしれません。
マダラテントウムシ亜科には注意
害虫を食べてくれるテントウムシは、ナナホシテントウムシやナミテントウムシなど種類です。見た目は普通のテントウムシでもニジュウヤホシテントウなどのマダラテントウムシ亜科の属す種類は、主食がナス科の葉っぱなので、ジャガイモの葉っぱなど綺麗さっぱり食べられてしまいます。益虫でモザイク病対策を考える場合は、虫の種類についてよく把握しておくようにしましょう。
モザイク病対策2:消毒
虫対策が完了したら、次に気にしたいことは消毒対策です。茎や葉っぱを刈り取ったときに飛び散る植物の体液に触れたものは、必ず消毒をして他の健康なプラントにモザイク病を移さないよう対策します。消毒方法は熱湯消毒、塩素消毒、レンテミン剤、を使用した消毒方法があります。
ハサミなどの器具は熱湯か塩素で消毒
剪定したり、モザイク病にかかった葉っぱを切り落としたりしたハサミは、モザイク病のウイルスが付着してい可能性があるので使用後は熱湯か塩素で消毒してください。使った器具が少なければ刃先に熱湯をかけて消毒しましょう、いくつもある場合は、バケツに水を張りハイターなどの塩素系洗浄剤を混ぜて(薄める濃度は0.1%未満)15分ほど漬け置きすれば消毒は完了です。サビが懸念されるので、濡らした刃物はすぐに乾いた布で水気を拭きとって下さい。
ラン科の植物にはレンテミン液剤
住友化学園芸 レンテミン液剤
ラン科の植物は他の草木よりもモザイク病が伝染しやすい特徴があるため、根っこのから放出される僅かな水分で感染してしまうことがあります。よってラン科の植物に限っては株分けで土壌を掘り返すときに、幹線経路が出来上がってしまうのです。それを防止するのが【住友化学園芸】のレンテミンという消毒液です。株分けのときに散布すれば、根っこを消毒して伝染を予防できます。※レンテミンはモザイク病を治す薬ではないのでご注意下さい。
モザイク病の作物は食べられるの?
モザイク病にかかってしまったら、もうどうすることもできません。残念ですが根っこから引き抜いて処分するしかないでしょう。しかし沢山の農作物が病気になってしまったら捨てるのは少し躊躇してしまい、モザイク病になった野菜や果物は食べられるのか、疑問に感じることがありますね。
見た目は気持ち悪くても食べられる
モザイク病はプラントにしか悪影響を与えないので、人が触れても飲み込んでも無害だと言われており、見た目は美味しくなさそうですが食べられるのです。果物に関しては、完熟してしまえばほとんどのモザイク病の傷跡は消えてしまうこともあるので、見た目に変化がない果物もあります。
モザイク病の作物の味はどうなの?
見た目は変でも食べられることが分かりました、しかし肝心なのはそのお味です。味に異変があればたとえ無害だとしても気持ち悪くて食べたくありません。モザイク病にかかった作物の味ですが、やはり多少の変化があるようです。
水分が豊富な果実の味の変化
トマトなど水分豊富な果実の場合は、味も食感も質が大きく低下するとされています。実がなる前や未熟時期にモザイク病にかかってしまえば、正常に育つことが困難になるので、見た目は緑や黒い斑点が付いたままで萎びた表面をしているの収穫することも厳しいでしょう。熟す途中の段階で発病した場合は、実の見た目はそこまで悪くなく、食べられるのですが、味は旨みがなく水っぽくて薄い印象を受けるでしょう。
ジャガイモのなどの根菜は比較的強い
ジャガイモはモザイク病にかかりやすい農作物と言われており、収穫したジャガイモにはモザイク病のウイルスが残留していることも珍しくありません。そのイモを種芋に使うと再びモザイク病が繁栄してしまいますが、人間が頂く分には特に問題なく食べられるのです。葉っぱの見た目は著しい変化が見られますが、ジャガイモ本体に関しては目立つ異変もなく、味は分からないと言っても過言ではないほど変化なしです。※ただし収穫量や芋のサイズに影響あり。
まとめ
モザイク病にかかってしまったら治ることはありません。そんあ厄介な病気から作物を守るには予防することがベターです。害虫対策と人の手による伝染促進を予防すれば、モザイク病の発症率は大幅に抑えることが出来るでしょう。ジャガイモなどの根菜に関しては、万が一病気にあっていても、味は変わらず美味しく食べられるので捨てる必要はありません。トマトやナス、スイカにメロンなどの野菜&果物は状況に応じて処分してください。
作物の病気について気になる方はこちらもチェック
モザイク病はほとんどの植物に発病する有名な病ですが、その他にも恐ろしい伝染病は沢山あります。被害情報や病気の特徴を知ってガーデニングをするうえでのリスクヘッジを試みたい方は、是非下記の関連記事を読んでみてください。

ベト病とは?気になる病気の原因や予防対策、治療方法まで徹底解説!
家庭菜園を襲う憎い病気・ベト病。ベト病とはいったいどんな症状が出る病気?かかりやすい植物の種類は?注意したい発生時期は?治療薬はある?無農薬...

植物の病気「さび病」の原因や対策方法をご紹介!葉裏にできる斑点には注意?
植物が赤くさびたようになってしまうさび病。放置しておくと植物を枯らすことも。今日は植物の葉裏にできる斑点である「さび病」についてとその治療法...

作物に被害のある「白絹病」ってどんな病気?その対策と治療方法はある?
家庭園芸を行うときに一番注意したいのが病害です。白絹病はいろいろな作物に発症する代表的な病害の一つ。白色の菌糸が土中で繁殖していき、対策をし...